違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~正月を祝う~
欧米人の正月の挨拶は“HAPPY NEW YEAR”だが日本人は「おめでとうございます」と言う。なぜ“正月はめでたい”のか?我々は正しい月と書いて正月と読むが、それでは正月の素顔は見えない。形容詞ではなく「正す」という動詞で考えると正月の実相が浮かび上がってくる。
言うなれば「正月」の七日間は心身を浄め新たな生命の誕生を願って万事を正しく整える月なのだ。各家々では門松を立て、その年の幸いをもたらす年神を迎える目印にする。門松は欧米のクリスマスの樅の木はその樹型から火・太陽・生命の象徴しているのと類似している点は興味深い。
『民俗学辞典』によれば「正月は年の初めで年の神を迎え、新しい年の実りを祈る祭りの月」とある。この“実りを祈る”とはなにか?それは“実り”を“稔り”と読むと理解できる。つまり稔は“トシ”と読み“稲の稔り”をもたらす穀霊を示している。稲の豊作を司る神の訪問に感謝し、神がお宿りになる鏡餅を供える床の間のある部屋を清浄な祭りの場として整え、神とともに過ごす晴れの七日間なのだ。
この七日間を「松の内(うち)」と呼ぶが、松には“神の降臨を待つ”という意味もある事も見逃せない。長寿と繁栄の祈りの象徴=松竹梅で祝うのはそのためだ。だから気軽な“HAPPY NEW YEAR”だけでは済まないのだ。
欧米人には正月は単なる通過点だが、我々には一年の始まりの重要な節目の日である。元旦は休日ではなく国の定める祝日になっているのもこうした背景があるからに他ならない。正月だからこそ、きちっと折り目を正す「お節料理」を食膳に供え、家族で祝い続けてきた“こころ”は忘れてはならないだろう。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~梅が匂う~
二月は暦の上では春…その春を告げる植物は梅。梅は冬の厳しい寒さに耐えて年の初めに咲くため、めでたい花として常緑の松や竹とともに慶木(けいぼく)とされている。寿命も長く梅の古木のなかには天然記念物に指定されている木もある。
ところで梅の原産地をご存知だろうか?それは中国だ。その中国との交流はとくに万葉の昔に盛んで、梅も当時の渡来物の一つとして貴族階級に歓迎された。
その証拠に『万葉集』には梅は百十八首も詠まれ、一番多い、萩についで二番目の数を誇り、代表的な万葉歌人の誰もが梅を詠んでいるが、なぜか柿本人麻呂の梅の歌はない。 梅の『万葉集』初登場は太宰府・大伴旅人の屋敷の梅見の宴で貴族たちが詠んだ三十二首(巻五)だ。当時、梅は大陸渡来の鑑賞花だった。言い換えれば貴族たちはその渡来花の高貴な匂いを嗅ぎ上等舶来!と酔いしれたのだろう。
たしかに梅には紅白があり、どこか風流な風情を感じさせる。その白梅が盛りを過ぎると紅梅が咲き出すが、その白梅と鶯をこよなく愛した江戸期の俳人は与謝蕪村。梅の色合いと匂いに反応する豊かな感性こそ、蕪村の魅力といえよう。
詩人の萩原朔太郎は、その著作『郷愁の詩人、与謝蕪村』の中で蕪村のリリシズムの新鮮さを讃えている。芭蕉のわび・さびの哲学的な世界に比べ、蕪村の俳句には鮮やかな艶(つや)があり、華やかな潤いに満ちている。梅を愛した蕪村の辞世の句は…
白梅の明(あく)る夜ばかりとなりにけり
臨終の床に集まった弟子にこの句に「初春」と題をおきさない、と言った逸話にも艶やかな人柄が偲べる。
ちなみに和英辞典で梅を引くとPLUMまたはUMEとある。また英語辞典でPLUMを引くとJAPANESE APRICOT=UMEとある。現在ではUME、HAIKU、KOBAN、TUNAMI、KARAOKE、KAWAIIはもう国際語だ。
来月は三月…もうすぐ春。
梅一輪 一輪ほどの暖かさ 嵐雪
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~雛に祈る~
梅についで桃も咲き初め吹く風も柔らかく本格的な春はもうすぐ…“野に出れば人みなやなしい桃の花”(高野素十)にめぐり会う三月は雛祭りの季節…。
巳日(みのひ)の祓(はら)いから生まれた雛祭り
昔、中国では奇数が重なる日を五節句に定めた。三月三日もその一つで「上巳(じょうみ)の節句」と呼ばれた。古代中国では三月の第一の巳(十二支のヘビ)の日を不浄を除く祓いの日とした。貴族たちは水辺に出て体を洗い清める禊(みそぎ)をして酒を飲み、災いを除く日とした。この日は朝廷では天皇が易学を司(つかさど)る役所(陰陽寮・おんみょうりょう)から奉られた人形(ひとがた)身体を撫で、息を吹きかけ着ていた単衣(ひとえ)の着物と一緒に家臣が川へ流したという。
この身体を撫で、穢(けが)れ移した人形を川や海へ流す風習が流し雛の原型だか、『源氏物語』の須磨の巻にも描かれている。それは今も鳥取・用瀬(もちがせ)町や和歌山・太地(たいち)の浦での雛流しの行事に今もみられる。人形は穢れを除くもののため俗に「雛人形は早く仕舞わないと嫁に行くのが遅れる」というのも厄祓いの撫でものだっから。なぜ桃を重視したののか…
『記紀』には桃の実で悪鬼を退治する神話があり、『西遊記』では西王母の桃には霊力をもつ仙果と記されている。桃の木で作った一対の人形を門口に立て魔除けにもしています。桃には邪を祓う呪力があるからこそ、庶民も神棚に桃の花を供え、御神酒に桃の花を挿して飲んだのも、桃の魔除けの霊力を信じたからに他ならない。
一方、お伽話の『桃太郎』は桃から生まれている。桃のタネを取ると空洞ができる。こに命が宿ると古代から信じられてきた。だからこそ桃の節句は子を産む女児の厄祓いと成長を祈る行事になった。撫でもの=人形(ひとがた)=雛人形への経緯は見逃せない。
◆親心を込めて雛人形を飾る…
室町期、将軍家へ家臣が祓いの意を込めて三月に人形一対を献上して以来、雛は夫婦雛となった。種類も多く段飾りになったのは江戸・享保頃…“段の雛、清水坂を一目哉”(其角)がある。江戸・中期以後、御所を象徴する桜、橘、随身(ずいしん)、家具・調度が加わり女児に嫁入りへの夢を抱かせた。また菱餅(ひしもち)は桃と同様、魔を祓う蓬(よもぎ)の餅に由来するように子の健やかな成長を祈る親心が伝わってくる。雛人形は、部屋中に春の陽光をあふれさせ、心まで浮き立たせてくれる。大伴家持も詠んでいる…
春の苑 紅(くれない)にほう桃の花 下照る道に出(い)でたつおとめ
雛人形はDoll、Puppetとは違う。単なる玩具でなく親心の祈りが籠った親子を結ぶ血潮にも似た愛の絆といえよう。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~桜に願う~
◆皛春を告げる“心の華”-桜
四月は春。いっせいに花開く季節…なかでも代表は桜。“三日見ぬ間の桜かな”という言葉もあるように桜は散りやすい。たしかに桜の花一つ一つは開花後、七日間程で散るが木全体では完全に散るまで約二週間も咲き続く。
この間に春の嵐に見舞われるので桜は“散る花”のイメージが強いのだろう。満開の姿が見事なだけに、散り際の潔(いさぎよ)さが讃えられ“花は桜木、人は武士”と言われ、桜は心の華として親しまれてきた。そして「花吹雪」や「花明かり」などの季語を生み、仰ぎみる人々に多彩な想いを抱かせてきた。“さまざまな事、思い出す桜かな(芭蕉)”はその一つ。
◆桜の美意識は『古今和歌集』以後…
『万葉集』には桜より梅が圧倒的。梅は中国からの渡来樹で色香が貴族に鑑賞花として珍重された。桜が詩歌に詠まれるのは『古今和歌集』以後…一方、農耕を営む先祖は田畑の仕事に入る時期に決まって咲くため「種(たね)蒔き桜」「田打つ桜」と呼んだ。
◆花見の始まりは信仰心から…
民俗学の折口信夫(しのぶ)は桜の「サ」は稲の神を示し」クラ」はその神が座る神座(かみくら)を指すと説いている。五月、五月雨(水垂れ)、早苗、早乙女すべて「サ」は稲にか関わっている。つまり桜は稲の稔りを左右する神の花だった。
もし、桜の花が早く散ればそれは神の力の衰えを示し、秋の凶作を暗示する。従って春の農作業に先駆け、桜の花の下で酒宴を開き、神に酒肴をすすめ、舞いを見せ、歌を聞かせて神を饗応し、桜が散らないように約束させ、秋の豊作を願った。これが“花見”の起源なのだ。
◆桜に込めた庶民の知恵と美意識
春の桜が秋の収穫につながるとなれば、桜の散るのを嫌うは当然。そこで生まれた神事の一つが“鎮花祭(ちんかさい)”。京都・紫野の今宮神社では四月の第二日曜日に行っている。別名、“安居祭(やすらいまつり)”と呼ばれている。桜花の散るのを鎮め、疫病神(えきびょうかみ)も“やすらぐ”事を願った祭りだ。
農事暦とは別に我が国では渓谷の清流に散って流れる桜の花びらを花筏(はないかだ)と名づけた美意識は、蒔絵師の手で洗練され、漆の工芸品を美しく飾った。
◆春に秋の収穫を祈ったのは東西共通…
Cheeryを辞書で引くと、上機嫌、愉快、活気づける、陽気にすると出ている。桜の咲く姿が華やかだからだろう。この花は人を快活にすると共に何か神の微笑みに会った気にさせる。古代ゲルマンの民俗に若い男女が森へ入り、サンザシの若い枝を折り、頭に被り秋の収穫を願った。春に芽吹く花のエネルギーに限りない生命力を感知した姿勢は東西共通といえよう。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~風が薫る~
◆風に色を見た美意識…
5月は緑の季節。芽吹き始めた街路樹の若葉も新しい季節の歓びを語りかけてくる。山々は日ごとに緑の衣装を重ね、鮮やかな新緑に萌えている。時折、山麓から一陣の風が駈ける上がっていく。斜面の青葉は風に靡き、初夏の陽光にキラキラと輝く。
木々を揺らす風こそ春の嵐だが、その風を私たちは「青嵐(あおあらし)」と呼んできた。大風は自然現象であるのにもかかわらず、単に嵐と言わず木々がざわめく姿に色彩を意識した点に日本人の風流な情緒が息づいていると言えよう。
◆薫風に泳ぐ鯉のぼり…
風は本来、無臭、無色だが、初夏に吹く風に人々は緑を感じ、薫りさえ実感し「薫風(くんぷう)」と名づけた。春の風が「光る」なら初夏の風は「薫る」のだ。風に光や薫りを感じるのは詩人の感性に他ならない。短歌に「風薫る」と用い始めたのは『新古今和歌集』(1205)以後という。
新緑には詩心とは別の意味でたしかに薫りがある。その薫りを科学の視線で追ってみると、梢の先で芽吹き始めた若葉から芳香性の強い微粒子を発散している。この微粒子はフィトンチッドと呼ばれ、細菌類を殺す作用を持っている。つまり植物が芽を吹き出すと、その若い芽を餌として狙う雑菌が近づく。それを追い払うため、植物は必死に強い香りを放つ。それが風に舞い、薫風となって遥かなる山里へ届くのだ。
この天然の香りあふれる風を、私たちは端午の節句に鯉のぼりのお腹にたっぷりと含ませて空高く泳がせてきた。鯉は出世魚と言われてきたため、鯉のぼりこそわが子の出世を願う親ごころの象徴でもある。
◆香りの強い菖蒲で災いを祓う
そしてこの季節、香りという点で見逃せないのが「菖蒲」だろう。根元の赤い部分に強い香りがある。西洋ではイリス・フローレンチーナという菖蒲に似た花の根は、香りが強いため歯磨き粉の香料に使われている。これに対してわが国では菖蒲の香りは邪気と不浄を祓う目的で使われてきた。
香料は貴重な薬だった。最近はプロ野球チームの優勝バーゲンの開店記念セールの際によく目にするがクスダマを割りのシーンだ。本来は開通した橋や道路に今後、一切の災いがないよう祈り祓うためだ。決して景気付けなどではない。この頃はクスダマを漢字で書ける日本人もへってきた。ただしくは「薬玉」と書く。香りの強い薬で厄祓いするのが本来の目的だからだ。たがら端午の節句には風呂に菖蒲を浮かせた「菖蒲湯」に入る。春から初夏へ季節が変化する、この時期に強い香りの精気で穢(けが)れを祓おうとした信仰心による。なお、菖蒲の鋭く尖った葉は日本刀に似ているため、菖蒲が尚武(武事を尊ぶこと)へ変化し男児の節句のシンボルになった事も見逃せない。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~雨に想う~
6月1日は「衣更え」。街行く人もすっかり夏姿へ…しとしと降り続いた春雨の恵みを受けて若葉は伸び、緑の葉脈を日一日と濃くしている。その艶やかな青葉をパラパラと手荒に打つ雨音が聞こえ始めると、もう本格的な雨のシーズン。
わが国には「雨期・乾期」の区別はなく、雨は四季を通じて降る。春の菜種梅雨、夏の白雨、秋の秋霖、冬の時雨(しぐれ)など、四季それぞれに呼び名がある。
といういう事はわが国の雨の多さを示している。
このように雨が年間を通じて多いのは日本の地形に起因する。たしかにわが日本列島は四面を海に囲まれ、その海から蒸発する水蒸気を含んだ湿った空気が、四季折々、季節風に運ばれ梅雨になり、秋の長雨になる。
さて「梅雨」という言葉は、元々は梅の実が熟す6月、7月にかけて中国・揚子江流域で降る長雨をこう呼んでいた。この降り方や時期がわが国の初夏の長雨(つゆ)と似ているため、この言葉が使われるようになった。この「つゆ」の語源は梅の実が「つはる(熟す)」から転じたとか…また物がカビる「つゆひ(損なわれる)」から由来したとか説はいろいろ…。
もっとも、生活を陰暦で過ごしてした時代、梅雨を「五月雨」と呼んでいた。
「サ」は「さつき(五月)」、「ミダレ」は「水垂れ」を意味する。この雨は田植え仕事を促すシグナルと考えられてきた。というのも「さつき」の「サ」は穀霊(稲の神)を示す古語で、長雨の季節には稲の実りをもたらす神が山から降りてくると信じていた。田へ迎えた神が早乙女の田植を手伝い励んでいるため、里の人々は五月を恋人との逢引を控える「物忌みの月」として謹慎の生活を行った。
降り続く雨の日々に昼夜を問わず、もの想いに沈み、胸を焦がし切ない恋の歌をとくに貴族たちは恋の歌を詠んだ。来る日も来る日も雨を眺めて暮らすため、いつしか「長雨」が「眺め」へ転じ、「ものの哀れ」の情感を育んできた。『広辞苑』の「ながめ」の項にも「もの想いにふける意味」と記している。現代でこそ「眺め」は遠くを見る意味だが、王朝の昔はやるせない哀しさを示す言葉だったとは…。見逃せないのは、この梅雨の長雨が私たち日本人にウエットな感性を培った点だ。長雨の湿りや翳(かげ)りは詩歌や小説、絵画に息づき、人の心の襞も豊かに潤している。
ちなみに英語辞典で雨を引くとRAIN、SHOWER、FALLの三語しかない。日本の場合、四季でみると雨をさす言葉は二十を越える。世界で「日本人は情緒人間」といわれるのはこうした気候風土に依る。もちろん人の人情だけでなく世界に誇る日本酒、味噌・醤油、寿司など発酵食品のすべてが梅雨の「湿気」の恵みで生きている。梅雨を鬱陶しいと嫌悪せず、長雨をむしろ誇りとすべきだろう。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~七夕に想う~
夏の夜のロマンは七夕だ。織女と牽牛が年に一度だけ出会うという伝説は、中国の後漢の時代(20~220年頃)に生まれている。この恋い物語の伝説を唐の時代の文人たちもてはやし7月7日の晩、開き恋人たちへ想いを寄せて星空を仰ぎ酒を酌み交わした。
わが国では奈良期の貴族たちがこの風流な遊宴を歓迎した。山上憶良もその一人で『万葉集』には七夕に因む和歌を12首残している。この他に『万葉集』には七夕伝説をテーマにした作品がなんと130首も集められていて、『古今和歌集』にも「秋の部」に七夕の和歌が見られる。
平安期の王朝人にとって、恋の切なさは我が事のように耐えがたかったに違いない。そのラブロマンスが手の届かない遥か彼方の星空の出来事だけに、彼らは憧れた事だろう。、皛なぜ「七夕」を「タナバタ」と読むのか?
この呼び方に疑問をもった諸君はいるだろうか?なんとも不思議な読み方ではないか!なぜ・どうして?と疑問を抱く以上に全く普通に我々は「タナバタ」と呼んできた。
この呼び方は我が国の「棚機つ女(たなばたつめ)」信仰に由来する。棚機つ女とは水の神に捧げる神聖な衣を織る神女をさす。河畔や湖畔、海辺に高い柱を立で支えた柵をつくり、小屋のような囲い、その場所で神女は籠って衣を織ったという。
また「七夕」つまり「七つの夕べ」という字が当てられるようになったのは、古く中国で7月7日に宮中で行っていた「乞巧奠(きこうでん)」という風習に由来する。この日の夜、織女伝説にあやかり、宮中では中庭には祭壇をつくり供物を供え、女性たちは七つの穴のある針に五色の糸を通し、裁縫の上達を祈って祭った。
「乞巧」とは「巧み(裁縫の技の上達)を乞う」事であり、「奠(でん)」とは「祭り」の意味を持つ。
江戸期、庶民し笹(神へ捧げる植物)に願い事を書きいた短冊を結び、翌日、川へ流し、今もなお「お習字がうまくなるように」と「手技(てわざ)」の上達を願う言葉を書く理由も分かるというものだ。今は川へものを流せないが、昔、人々は川を司る水の神へ願い事を叶えて貰おうとした名残りといえる。なぜ川へ流したのか?
それはお盆の精霊流しのように川へ洗い流す事が「祓い・浄め」の意味だった。
また稲作をする農村では七夕の頃の七月上旬(旧暦)には水田へ水を入れる「水口祭り」を行う時期でもある。風流心より、大切な生活の節目の行事として行われた。
いずれにしても「七夕」は星の伝説、棚機つ女の信仰、七(奇数)を尊ぶ陰陽道、乞巧奠の風習、水に流す祓いの神事、稲作の農事暦などが渾然一体化し継承されてきた複雑な行事なのだ。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~盆に踊る~
夏の夜の風物詩といえば盆踊りだろう。紅白幕を引いた櫓(やぐら)の上では太鼓と笛の音(ね)が快く響く…その下では団扇(うちわ)を手にした浴衣姿の老若男女が輪になって踊る。吊り下げられた提灯の灯りが夏の夜の涼風に揺れている。
会場は寺の境内か町の広場が最近、会場になっている。だが江戸の昔は月の明かりだけの演出だった様子は蕪村が詠んだ“四、五人に月落ちかかる踊りかな”からもわかる。俳諧で踊りといえば盆踊りをさし、盆の三日間、踊った。
なぜ踊るのか?理由はあの世へ逝った死者が盆には供養を求めて帰ってくる。
その精霊たちを慰めるために踊ったのが本来のようだ。と同時に餓鬼(がき)=死後、空腹に苦しむ亡者=を供養する意図もあった。餓鬼とは無縁仏や成仏できない怨霊(おんりょう)をさし、そうした霊のため、静かに踊ったのが本来の姿だった。その代表が富山・八尾(やつお)の「風の盆」。信仰心のあらわれであり、単なる観光ではない。
ところで盆踊りはなぜ夜なのか?楽しみの少ない昔、夜のレジャーとしたわけではない。もっと重要な意味がある。つまりわが国の祭りの古式では宵に神々を迎え、宵祭りの神事の後、神楽(かぐら)を奉納し直会(なおらい・神に捧げた供物による食事の宴)を行い、灯明(とうみょう)を絶やさず人々は夜籠りをする。夜籠りに祭りの本義が濃縮されている。当時、夜の闇は神聖なる空間だ。闇夜に映える提灯こそ、仏前に供える灯明と同じだ。
盆は霊祭りとも言い、八月十五日、いわゆる旧盆に行う地方が多い。ビジネス街でもこの日の前後は暑中休暇となり空っぽになる。本来はこの期間に帰省したり墓参りをする。
ちなみに盆の語源は何か?諸説あるが古代イラン語の「ウルバン」(死者の霊魂の意)に由来するという説もある。この霊魂を祀る風習が中国で仏教徒に受け継がれ日本へ伝来したものと思える。『枕草子』にも載っている事からも古くからの行事と言えよう。
精霊を迎えるために庭先に供物を供える盆棚をつくり、座敷に盆提灯を灯し、十三日の夕刻、門口では苧殻(おがら)を焚き祖霊を迎える。そして三日後、精霊をまた火で送る。とくに京都で行う大文字の送り火が有名…この火は精霊の帰り道を明るく照らすもののため、大きく燃え上がる勢いのある火でなければならない。
盆行事は正月と違い送り迎えの期間が慌ただしく心残りを感じる。この点、角川書店の創業者・角川源義が句に詠んだ。
盆三日あまり短かし帰る刻(とき)
いずれにしても盆には先祖がこの世へ帰ってくる。迎え火で祖霊を迎え、家族揃って墓参りをしょう。盆こそ祖霊と対話できる好機だが、外国ではどうやって祖先と対話するのだろうか?チッと気になるところだ。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~月を観る~
皛畑の作物に感謝する十五夜の祭り
月々に月みる月は多けれど
月みる月はこの月り月
ここでいう「この月の月」はいうまでもなく十五夜の「中秋」の名月をさす。
わが国の暦は太陽暦へ移行するまで、月の運行を基準にする太陰暦だった。月々の満月を節目にするため、年の初めも元日ではなく、正月の満月の夜が年の境だった。
そのため日常でも月の文化は多岐にわたり月は農耕生活の基本だった。例えば民俗学ではハルゴト・オイゴトと呼ぶ三月十五日は地の神、田の神が里へ降りる日であり、そして十月十五日は山へ帰られる日とされていた。
ではなぜ旧暦八月十五日の日を名月と讃えてきたのだろうか。丁度、この頃は農作物の収穫時期のため、実りに感謝する日だった。つまりこの日はその年、収穫した穀物、野菜、果物を神仏へ供える、いわば野菜の初穂(はつほ)祭り。かつてこの日は稲穂に見立てたススキをはじめ、再生霊が宿ると信じられた里芋、団子、枝豆など畑の作物を供えた。
なぜ里芋なのか?それは縄文期に日本列島へ渡来した南方系の人種がタロイモを持ち込んだ。そのDNAがインプットされ、それが平成の今日まで受け継がれているのは驚きだ。
わが国の月の神は月読命(つくよみのみこと)。ツクは月、ヨミは数えるの意味…つまり月の運行を司る暦の神であり、農事を占う神でもある。だからこそ、「お月見」をする。江戸っ子も十五夜の月を仰ぎ、月のお陰に感謝し酒肴の宴を開いて残した川柳は「上戸にも下戸にもできる月見かな」。現代人の野菜摂取量は極端にすくない。月見の宴を契機に肉を控えて野菜の摂取に心掛けよう!
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~相撲を取る~
九月場所は終わった。次の本場所、九州場所は11月に始まる。ここ数年、モンゴル旋風が吹き荒れているが、忘れてならないのは相撲は日本の国技である事を。
相撲の歴史は古く『日本書紀』には野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)の天覧相撲の記事がある。宿禰は後に神となり、東京・両国に宿禰神社がある。一方古墳の遺物に褌(ふんどし)を締めた力士の埴輪が発掘されている。埴輪は六世紀頃と推定されるから、その頃から相撲が取られていた事がわかる。
天覧相撲から発しただけに、やがて絢爛豪華な様式美の「相撲の式」となり、国家安泰、五穀豊饒を祈念し、農作物の豊凶を占う「国占い」へと変化した。これが相撲の原形となった典型の農耕儀礼がある。それが愛媛県・大山祇(おおやまずみ)神社の「一人角力」。一人の力士が目には見えない稲の精霊と相撲を取り一勝二敗で精霊が勝つ。だから相撲は東西どちらが豊作かを占うのがそもそもの起源だ。それは見逃せない。
ここには神へ相撲を奉納し豊饒を願った庶民の信仰心が窺え、さらに古代の相撲節会という国家的な行事となり、明治末、相撲は「国技」と呼ばれるようになった。神事相撲の伝統は現代へ継承されている。土俵の上の吊り屋根は伊勢神宮の神明(しんめい)造り、四隅の房は四季と各方向の主護神の象徴。また屋根を囲う紫の水引幕や清めの塩で土俵という「聖なる空間」を演出している。
また力士の大銀杏の髪型や公家の礼法に拠った行司の色彩ゆたかな衣装、軍配には様式美が息づいている。四股名は今も力士の故郷の海・山にちなみ、横綱は神社の「しめ縄」を思わせ、正式には「産霊(むすび)の神緒」という。ここにも神事の面影が濃い。さらに土俵入りの「型」の「雲龍」は亀を象り地を表し、「不知火(しらぬい)」は鶴を象り天を表している。
これをみても相撲は信仰心をペースに神事の様式美を大切にする国技であるといえる。櫓太鼓の響き、風になびく幟、力士の化粧廻し、呼び出しの裁着袴(たっけつはかま)や澄んだ美声…すべてが様式美。
勝敗にのみ興味を寄せずに伝統の様式美に目を凝らし、耳を澄ませてば、相撲は単なる格闘技でない事がわかる。蹲踞(そんきょ)の姿勢や手刀(てがたな)の切り方、力水のつけ方など動作一つ一つに「礼に始まり礼に終わる」相撲の心は忘れてはならない。最近、国技と言い難い我慢ができない相撲ぶりを目にする事が多くなったと思うのは私だけだろうか?海外巡業もいいけれど力士を「相撲レスラー」と呼ぶのはやめてほしい!勝てばいい、という競技ではないのだから!
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J
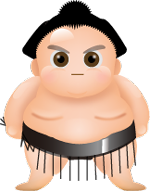
違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~七五三を祝う~
銀杏が色づき枯葉が舞い散る…空気まで黄金色にそまる十一月…初冬の澄み切った空の下、「七五三」の宮参りへ向かう親子の晴姿が見られる季節になりました。
秋から冬へ季節が替わる時期に行われるのが「七五三」のお祝いです。数え年で三歳と五歳の男の子、三歳と七歳の女の子を祝い健康と成長を願う伝統の行事です。もともとは徳川三代将軍・家光の四男徳松(後の五代将軍綱吉)の身体が虚弱のため、五歳の祝いを慶安三(一六五〇)年の十一月十五日に行ったのが始まりのようです。
なぜ十一月十五日なのでしょう。理由は昔の暦によれば丁度、この日が「鬼宿日(きしゅくにち)」にあたり、婚礼以外は万事に「大吉」、いわば大安吉日の元祖といえる、誠にめでたい祝い日だったからです。こうした吉日にさらに将軍の権威が重なり、この日が決められたのでしょう。従って「七五三」は子供が災禍に負けぬ抵抗力をつける節目(ふしめ) の歳祝いです。そのため、めでたいから祝うのではなく、祝うことでめでたくするという信仰に由来しています。
七歳、五歳、三歳の奇数に整えられたのは中国の名数(めいすう)信仰によります。これは陰陽五行説(万物は陰と陽で生じるという哲学)に発します。数字も陰(偶数)陽(奇数)に分け、陽数(奇数)は縁起のいい数字とみなし、なかでも七歳は子供の成長過程でもっとも大きな関門でした。
かつて「七つ前は神のうち」といわれたように、七歳までは罪も咎められず、社会の一員とも認められませんでした。そこで氏子(うじこ) 入りと称し氏神(うじがみ)へ参って、初めて神からも社会からも承認され、祝福される七歳の式が必要だったのです。七歳になると共同体の一員として認められ、受け入れられるという村づきあいの掟が昔、日本の各地の村落にあったのです。
この取り決めにより共同体一人一人の権利と義務が生じてきますが、村を支える新しい構成員として村の大人たちからも守護を得、氏神の加護を祈ったのが「七五三」の本来の姿だったのです。
江戸中期には長寿を願う「千歳飴」も売りだされ、衣装も華美を競うようになり、川柳も、「帯と袴で呉服屋へ十二両」と「七五三」の七と五を足して詠んでいます。また祝福と愛情をユーモアをこめた川柳もあります。「礼服で乳を飲んでる十五日」「神前へ車で参る七五三」は父親が幼な子を肩車にのせ、お参りする姿は庶民の温かい親ごころを伝えています。
─酉(とり)の市─
十一月の酉の日に各地の鷲(おおとり)神社で行われる祭礼で、東京下谷の鷲(おおとり)神社が江戸期から有名です。十一月の最初の酉の日を「一の酉」と言い、順次、「二の酉」「三の酉」と呼びます。年によって「三の酉」まである年は火事が多いと俗に言われています。
本来は武運を祈る神として武士に信仰されていましたが、後に客商売の者が縁起をかついで多く参拝しました。その結果、現在では、開運・商売繁盛の神として信仰され、祭りの期間、参道には「福」を掻きこむ熊手・おかめの面・宝船・大判・小判などの縁起物が売られ、多数の参詣人で賑わいます。
不景気になると人はだれでも「神頼み」に縋るようになるのは今も昔も変わらなかった点は興味深いといえましょう。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

違いを知る若き国際人へ贈る日本文化ガイド
~鐘が響く~
一年の総仕舞をする十二月。各寺院では大晦日の十二時から除夜の鐘を撞き出す。
大晦日も午前零時になると、寺々で撞きだす鐘が百八つの煩悩を一つ一つ打ち破っていきます。 寺院の鐘は元来、朝夕に撞くのが習わしだ。朝、撞く鐘は暁鐘といい、眠りを覚まさせるためで、夕方の晩鐘は迷い易い心を戒めるもの…。
鐘には梵鐘(大鐘・釣鐘)と喚鐘(小鐘)があります。喚鐘はおもに人々を呼び集めるのに使い、除夜に撞くのは梵鐘(ぼんしょう)。なぜ鐘をつくのか?それは古くから鐘の音や鈴の音に不浄を淨める働きを先祖は意識してきたからだ。つまり除夜の鐘は一年の不浄を淨めるために撞く。
その除夜とは除目(じょもく・旧年を取り去る日)の夜をさし、大晦日の夜を意味する。この夜、人々は鐘の響きに耳を傾け、越し方、行く末に思いを馳せる。師走の空の下、星々は霜夜の闇に光り、鐘の音は凍てつく風にのり余韻を残す…。
その師走の語源はどこからきたか?それは古くは十二月に亡き祖霊(先祖の霊)を祀る行事があり、僧侶が駆け足で檀家廻りをした。そこからシハセ(師馳せ)に由来という説が有力…だが「年果つる月」「物事をしはつる月」という説もある。
忙しいだけでなく十二月は早く春を呼びたいと願う月でもある。歳時記には春待ち月、梅初(うめはつ)月があり、新しい年に人の心を浮き立つ。そんななかで一年を振り返ると、希因が詠んだ句-「行く年や同じことして水車(みずぐるま)」が一層、悔恨の情が胸に迫る。
いずれにしても大晦日は独り静かに「年越しの湯」に身を沈め立ちのぼる湯気に想いを馳せてみては如何?そして洗い場ではまず足の裏から洗ってほしい…足の裏は目立つ事なくこの一年、支え通してくれた…丁度、人生において誰もが誰かに支えられて生きていると語るかのような足の裏に心からの感謝を込めて“有り難う”と声を掛けながら…。
国際人とは自国の文化という鏡で異文化を映し“違い”を理解する事が第一条件だ。
各民族が互いに違いを認め合ってこそ国際化といえよう。誇りをもって自己への認識を深め、相手国を理解するためにも、若人よ!確かな鏡をもとう!
S. Y. J

同窓会よ 橙と紺の鮮やかな組紐であれ
我々はさまざまな縁(えにし)のなかで多様な糸に結ばれ社会生活を営んでいる。我等が同窓会も同様…。卒業生と在校生、さらに学校と大学とオレンジとブルーの糸で結ばれ、その「結び目」に同窓会が位置している。「結」という字は会意兼形声文字で“糸や紐で入る口をしっかりとくびる事”と漢和辞典にある。
その背景から“しっかりした結束の強さ”が浮かび上がる。この「結」こそ同窓会のキーワードになるのではないか?因に「結(ゆい)」を辞書でを引くと“田植えや屋根替え、味噌搗きなど、一時に多くの労力を要する際、お互いに人手を貸し合う事”とある。つまり互いに助け合う結束の強い姿勢は現代の言葉で換言すれば「組織」そのものとも言えよう。
「組」は“ソ”と訓じ“くむ”とも読む。さらに組の旁(つくり)「且(しゃ)」は物を重ねたさまを示す事から「組」だけでも何本かの太糸を上へ上へと重ねるように編んむ組紐(くみひも)をも意味する。
“多寡が紐”と言ってはならない。単なる一本の組紐といっても我が国の「紐(ひも)」は考古学・歴史学・美術史・民俗学・風俗学にわたる膨大な要素を内蔵している。いま各分野への探索は避けるが、一般に紐は端と端を「結んで」初めて機能する。
ここで「組織」の核を成す「結(ゆい)」との共通点を改めて意識するのは当然だろう。と同時に「結い」に由来する「結ぶ」の語源の「産(む)す」へ好奇心がそそられる。
では「産(む)す」とはなに?「産」の字は『古事記』の冒頭に登場する造化三神の一人=高皇産霊神(たかみむすびのかみ)にみられる。この「産」は“生み出す”の意だ。唐突だが我々男子は両親から生まれた“息子(むすこ)”で姉や妹は“娘(むすめ)”だ。共通しているのはどちらにも“むす”がある。つまり両親が「結ばれ」=「産した」結果が我々なのだ。
このように「結い」=「結ぶ」=「産(む)す」は身近に存在するが、古く縄文期の土器に残された圧痕=縄目の文様も撚り紐とする説もある。縄も紐も“撚り合わされたもの”でこれは意外にも“蛇のイメージ”に基づいていると言われている。
なぜ蛇なのか?古代の人々は蛇の脱皮の習性に生命の再生を凝視したからに他ならない。その逞しい生命力はいまも“神社のしめ縄”になり、相撲の横綱の“綱そのもの”にも継承されている。活力の象徴とした心が明瞭だ。
結論を急ごう。同窓会は人と人との結び付きで成り立ち、多くの人材で支えられている。願わくば同窓会よ、鮮やかな組紐であれ!色どりも多彩にエネルギッシュな輝きこそ、いま求められているのではないだろうか?
佐伯 仁(第13期)
